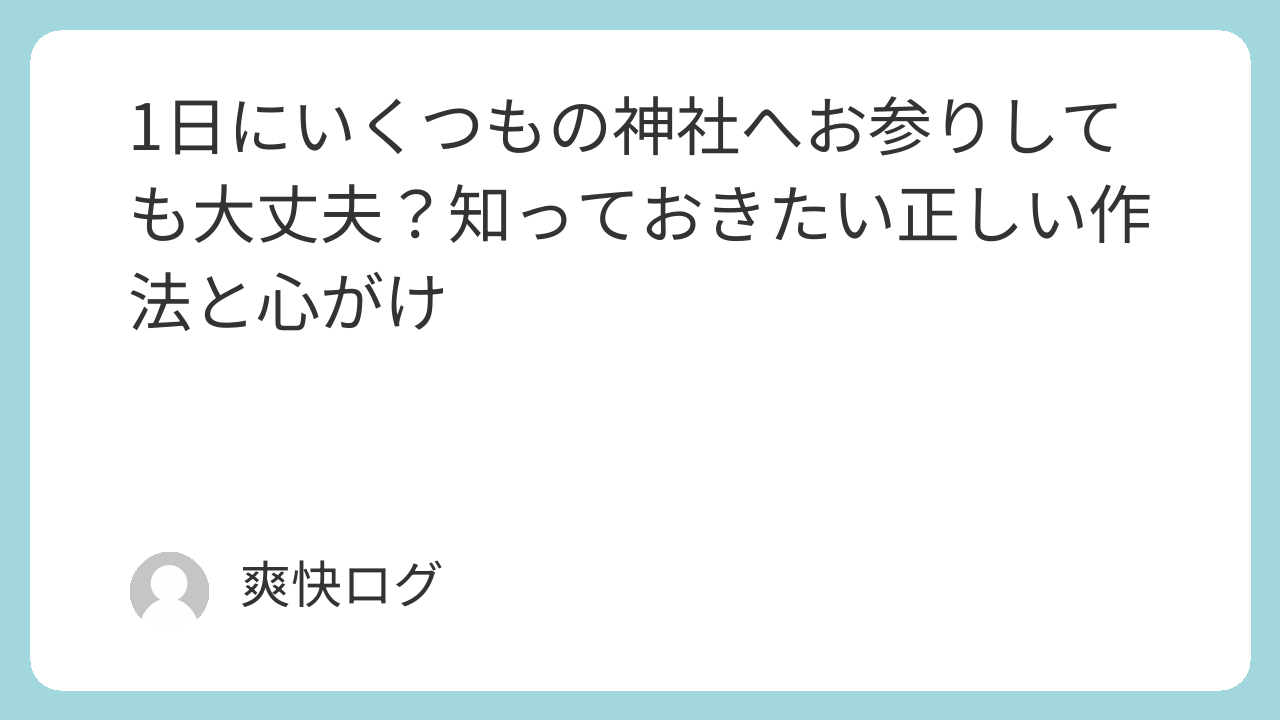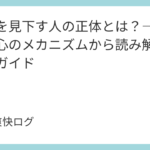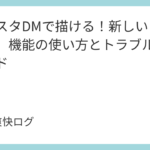神社巡りが好きな方や、旅行先で複数の神社を訪れる方も多いですよね。歴史ある社殿や厳かな空気、自然に囲まれた境内を歩く時間は、心をリセットするような特別なひとときです。
しかし、「1日にいくつも参拝すると神様に失礼では?」と不安に感じる方も少なくありません。中には「同じ日に複数の神様にお願いしてはいけないのでは?」と戸惑う方もいるでしょう。
けれども、実は神道の世界では、参拝の回数や順番よりもずっと大切なのは“気持ちの持ち方”です。どの神社でも共通して大切にされているのは、感謝と敬意の心。神様を思い、心をこめて手を合わせることこそが正しい参拝のあり方なのです。
この記事では、初心者の方にもわかりやすいように、1日に複数の神社をお参りする際の考え方、基本のマナー、そして心を整えるための心得を、実際の例を交えながら丁寧にご紹介します。読んだあとにすぐに実践できるポイントも盛り込みましたので、初めて神社巡りをされる方にも安心してご覧いただけます。
違う神社を1日に回ってもいいの?

神道の考え方から見る「一日複数参拝」
神道では、神様同士が喧嘩をしたり嫉妬をしたりするという考えはありません。
むしろ多くの神社をお参りすることで、神々とのご縁を広げる行いとして前向きに受け止められています。神道の教えでは、八百万の神々がそれぞれに役割を持ち、すべてが調和して世の中を支えていると考えられています。ですから、複数の神社に足を運ぶことは、さまざまな神様とつながり、感謝を伝える貴重な機会になるのです。重要なのは「欲張るためではなく、感謝と誠意を伝えるため」にお参りすること。欲求を満たすための行為ではなく、自分を見つめ直し、心を整える時間として参拝すると、自然と穏やかな気持ちになります。
二社参りは失礼になる?神職の見解
多くの神職の方は「複数の神社に参拝しても失礼にはあたらない」と話されています。神様は人の外見や数よりも、心のあり方を重んじておられます。
つまり、どれだけ多くお参りしたかではなく、どれだけ真摯に手を合わせたかが大切なのです。また、参拝する際に神社ごとの由緒やご祭神に思いを寄せると、自然と丁寧な姿勢が身につきます。ひとつひとつの神社を心を込めて訪ねることこそ、最も美しい参拝の形といえるでしょう。
誤解されがちなマナー違反
「複数参拝すると願いが分散する」「最初の神様が怒る」といった話はよく耳にしますが、これは俗説にすぎません。
神道の根本は調和と共存にあり、神々は互いを尊重し合っています。神様を“競わせる”ような気持ちでなければ、複数参拝はむしろ心を清め、より謙虚な気持ちを育てる機会になります。例えば旅の途中で複数の神社を巡ることで、それぞれの土地の神様への感謝を深めるきっかけにもなるでしょう。
地域や風習による違い
伊勢神宮や出雲大社など、「複数の社を巡ること」が古くから文化として根付いている場所も多くあります。「お伊勢参り」「七社参り」など、古くから日本各地に伝わる風習も同様です。
地域ごとにその土地の神様をたたえる伝統があり、複数の神社を訪ねること自体が信仰の証でもあります。現代でも旅先でいくつもの神社を巡る人が増えていますが、これは昔の文化が自然な形で受け継がれているとも言えます。
ご縁をつなぐ参拝の心構え
神社ごとにご利益や祀られている神様の役割は異なります。
たとえば、学業成就の神様、縁結びの神様、厄除けの神様と、それぞれに異なるお力をお持ちです。それぞれのご縁に感謝し、今ある自分を受け入れながら祈ることで、心の整理がつき、自然と前向きなエネルギーが湧いてきます。参拝の本質は“祈り”よりも“感謝”。一社一社の神様に敬意をもって手を合わせることで、自分自身の心も美しく整っていくのです。
神社をはしご参拝するメリットと注意点

ご利益と目的を明確にする
複数参拝には「ご縁を広げる」「心を整える」といった意味があります。はしご参拝をすることで、神様ごとに違うご加護や教えを受け取れると考える人も多いです。
例えば、一社目では感謝を、二社目では新たな誓いを立てるなど、自分の気持ちにテーマを持たせると心が整理されやすくなります。ただし、欲張らず、神様ごとに感謝と願いを込めて参拝することが大切です。すべての神様に対して誠意をもって向き合う姿勢が、最も美しいはしご参拝の形です。
参拝の順番や距離に意味はある?
厳密な決まりはありませんが、「遠い神社から近い神社へ」「有名な神社を最後に」といった順序を意識すると、旅全体に流れが生まれます。
実際、昔のお伊勢参りや七社参りでも順番に意味を持たせることが多く、心の流れを整える知恵として伝えられてきました。地図を見ながら計画を立てると、余裕をもって行動でき、参拝そのものをより丁寧に楽しむことができます。また、神社ごとに異なる空気感を感じるためにも、少し時間を置いて移動するのが理想的です。
お賽銭の額は気持ちで決めてOK
お賽銭は「心を捧げる」という意味があるため、金額よりも真心が大切です。
一般的には5円(ご縁)や15円(十分なご縁)など語呂合わせで選ぶ方もいますが、それもあくまで目安。
どんな金額でも、感謝の気持ちを込めて手を合わせることが大切です。複数の神社を回る場合は同じ額にこだわらず、その時の気持ちで決めましょう。財布の小銭を整える、事前にきれいな硬貨を用意するなど、準備のひと手間にも敬意が表れます。
時間を空けるべき?
午前と午後で分けたり、移動の間に一息ついたりすることで、気持ちの切り替えがしやすくなります。
特に、神社ごとに祀られている神様が異なる場合は、短い休憩や軽い食事をはさむことで心が落ち着き、より丁寧に参拝できるでしょう。とはいえ、同じ日に複数参拝しても全く問題はありません。むしろ、「一日を通して感謝の気持ちを重ねていく」という心持ちで臨むと、自然と清々しい気分になります。
願い事を分けるときの注意
複数の神社で同じ願いをしても構いませんが、それぞれの神様の御神徳に合わせて言葉を変えると、より誠実な印象になります。
例えば、学問の神様には努力が実るよう祈り、縁結びの神様には良縁を感謝しながら願うなど、神社ごとに意識を変えることがポイントです。お願い事ばかりでなく「これまでのご加護への感謝」も忘れずに伝えることで、心がより穏やかに整っていきます。願いを叶えるための祈りではなく、日々を見つめ直す時間としての参拝を心がけましょう。
同じ神社に2回お参りしても大丈夫?
短時間で再訪する場合
参拝後にもう一度立ち寄っても失礼ではありません。たとえば御朱印をもらい忘れた場合や、社務所が混雑していて後で再訪するケースなど、日常的によくあることです。その際は、初回と同じように鳥居の前で一礼し、感謝の気持ちをもって境内に入りましょう。神様は形式よりも、あなたの誠意を見ています。
二度目の参拝でも、静かに深呼吸をして心を整えると、より穏やかな気持ちで手を合わせられます。
ご祈祷や御朱印のための再訪
ご祈祷や厄払い、御朱印の授与など特別な目的で再び訪れる場合もまったく問題ありません。それぞれの行為には意味があり、神様はその心を理解してくださいます。
特にご祈祷は、神職の方を通して願いを正式に伝える神聖な儀式。再訪の際には服装や姿勢にも気を配り、静かに待つことで、神様や他の参拝者への敬意を表せます。御朱印もまた、「参拝の証」をいただく行為。焦らず、感謝の気持ちをもって受け取ることが大切です。
境内への入り方と姿勢
再入場する際も、鳥居の前で軽く一礼してから足を踏み入れましょう。境内では声を潜め、歩くときは端を静かに歩くのが望ましいです。写真を撮るときは他の参拝者や神職の妨げにならないよう配慮し、拝殿ではカメラを向けないことが基本です。再訪だからと気を抜かず、一回目と同じ気持ちで丁寧に行動することが、神様への礼儀になります。
お守りやお札を追加でもらうとき
複数の御守りを持つことは、複数の神様から見守られるという意味でもあり、決して悪いことではありません。交通安全や健康祈願など、目的に応じてお守りを持ち分けるのも良いでしょう。
ただし、古いお守りは年末や初詣の際に感謝してお返しするのが礼儀です。神社によっては専用の返納箱があるため、そこに静かに納めましょう。持ち歩く際も粗末に扱わず、清潔なポーチや財布などに丁寧にしまうと、より良いご加護をいただけます。
待ち時間中の過ごし方
御朱印やご祈祷の順番を待つ間は、スマホを見続けるよりも、心を落ち着けて境内の空気を感じましょう。木々のそよぎや鳥の声に耳を傾けるだけで、不思議と心が軽くなるはずです。神社での待ち時間は“神様と向き合う静かな時間”と考えるのが理想です。周囲の方とおしゃべりする場合も小声で控えめに。そうした一つひとつの所作が、神聖な空間を守る行いにつながります。
参拝の前に知っておきたい準備と心得

服装と持ち物のマナー
露出の少ない清潔な服装が理想です。派手すぎる格好や強い香水は避けましょう。手水舎で手や口を清めるため、ハンカチも持参を。
特に女性は、動きやすい靴や控えめなアクセサリーを選ぶと上品な印象になります。
男性も襟付きのシャツなど清潔感のある服装が望ましいです。また、帽子をかぶっている場合は参拝時に外すとより丁寧です。小さな布袋やサコッシュに財布とお賽銭、ハンカチを入れておくと身軽に動けます。
感謝の気持ちを大切に
お願い事よりも、まず「日々守ってくださる感謝」を伝えることが基本。心が整い、自然と良いご縁を呼び込みます。たとえ願いがあっても、最初の一礼では「今日もお参りさせていただけることへの感謝」を伝えるようにしましょう。神様に感謝の言葉を心の中で唱えるだけでも、気持ちが穏やかになります。感謝の積み重ねが信仰心を育て、より強いご縁を結ぶことにつながります。
家族や友人と参拝する場合
列を乱さず、話し声は控えめに。子どもと一緒のときは、手をつないで安全に行動しましょう。家族連れの参拝では、全員が順番に手を合わせる時間を作ると良いでしょう。小さな子どもには、手を洗う意味やお辞儀の仕方をやさしく教えてあげることで、信仰心を自然に育むことができます。友人同士で参拝する場合も、境内ではおしゃべりを控え、神様の前では静かに心を向ける姿勢を大切にしましょう。
天候・季節ごとの注意点
雨の日は滑りやすいので靴選びに注意を。真夏は日傘、冬は防寒対策をしっかりと行いましょう。冬場は手袋をしてもかまいませんが、拝礼のときは外すとより丁寧です。春や秋は花粉や落ち葉などに注意し、ハンカチやティッシュを多めに持っておくと安心です。どんな季節でも「清潔さ」と「落ち着いた所作」を意識すると、神聖な空間になじみます。
スマホの扱い方
撮影禁止の場所もあります。撮る前に注意書きを確認し、祈祷やお参り中はスマホをしまうのが礼儀です。
SNS投稿をする際も、神社の名前や御神体が写っている写真は控えめに扱いましょう。連絡や地図の確認のために使用するのは構いませんが、参拝中は一度電源を切るかマナーモードにしておくのが理想です。スマホの扱い方ひとつでも、神様や他の参拝者への敬意が伝わります。
行事や特別な参拝時のマナー

初詣・七五三・お宮参りなどの違い
それぞれの行事には深い意味があります。初詣は新しい年を迎える際に、無事に年を越せた感謝を伝え、これからの一年の健康や幸福を祈る行事です。七五三は子どもの成長を祝い、これからも健やかに過ごせるよう祈る日。お宮参りは、生まれて初めて赤ちゃんを神様にお披露目する大切な儀式です。
これらの行事では「お願い」よりも「感謝」と「報告」の心が基本です。服装は華美すぎず清楚に、家族全員で静かに手を合わせる姿勢を意識すると良いでしょう。
喪中・葬儀の際はどうする?
喪中の期間は神社参拝を控えるのが一般的です。これは、神道において「死」は穢れ(けがれ)とされ、一定期間は神前に立つことを慎むためです。
ただし、忌明け(四十九日)を過ぎれば問題ありません。どうしてもお参りしたい場合や心を整えたい場合は、鳥居の外から軽く一礼し、遠くから手を合わせるだけでも十分です。神社によって対応が異なることもあるので、社務所で相談してから参拝すると安心です。心からの祈りがあれば、神様はその気持ちをきっと受け取ってくださいます。
特別な願い事の伝え方
願いを伝えるときは、できるだけ簡潔に、自分の努力を前提とした言葉で祈るのがポイントです。たとえば「合格できますように」ではなく「努力を実らせることができますように」というように、前向きで謙虚な言葉を使いましょう。
また、願いの前に「いつも見守ってくださりありがとうございます」と感謝を添えることで、より誠意のある祈りになります。声に出さなくても心の中で丁寧に伝えるだけで十分です。神様は言葉よりも心の真実を見てくださいます。
願いごとの種類別の心構え
恋愛・金運・健康・仕事など、それぞれの目的で参拝する場合でも、共通して大切なのは「感謝の気持ち」です。
恋愛祈願では「良いご縁を与えてください」よりも「素直な心で人と向き合えますように」と祈ると、より前向きなご加護が得られると言われています。金運や仕事の祈願では、努力の成果が正しく実るよう願うことが基本です。健康祈願は「病を退けてほしい」ではなく「健やかに生きる力をください」と伝えると、日々への感謝と共に前向きなエネルギーが湧いてきます。
旅行中の観光参拝
観光地の神社では写真を撮る方も多いですが、参拝前にお辞儀をしてから撮影するなど、感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。
撮影の際は他の参拝者や神職の邪魔にならないようにし、祈祷中や拝殿内では撮影を控えるのがマナーです。旅先での参拝は、その土地の神様に「訪問のご挨拶」をする気持ちで臨むと良いでしょう。
また、旅の安全を祈願することで、道中がより穏やかで充実したものになります。帰宅後には「無事に帰れたお礼参り」をするのも丁寧な習わしです。
参拝後の心得と次へのつなげ方
参拝の効果を感じるには
「ご利益があったかどうか」を気にするよりも、参拝のあとに自分の気持ちがどう変化したかを意識してみましょう。
神社で手を合わせたあと、心が軽くなったり、前向きな気持ちになったりするなら、それこそがご利益の現れです。神様は私たちの日々の努力や感謝を通して、少しずつ心を導いてくださいます。小さな変化でも「自分が落ち着いている」「感謝できている」と気づけたら、それを大切にしていきましょう。内省しながら、自分の成長を感じる時間を持つことが、本当の参拝の意味につながります。
おみくじや占いの活かし方
おみくじや占いは未来を断定するものではなく、“今の自分に必要な気づき”を教えてくれるヒントです。結果に一喜一憂せず、「今後どうすれば良い方向に進めるか」を考えるきっかけにしましょう。
たとえ凶が出ても、それは「油断せず慎重に進めば大丈夫」という神様からのアドバイスです。良い結果でも、努力を忘れず謙虚に行動することが大切です。引いたおみくじは境内の結び所に結んでも、持ち帰って見返しても構いません。自分の心の支えとして、前向きに受け取ることが理想です。
定期的な参拝を続けるコツ
参拝は特別な行事としてだけでなく、日常の延長として取り入れると心が整いやすくなります。季節の変わり目や月の初めなど、自分なりのタイミングを決めておくと無理なく続けられます。
例えば「新月や満月の日に感謝の参拝をする」「節分やお盆の時期に家族でお参りする」といった習慣を作るのもおすすめです。定期的に訪れることで、神社の空気の変化や自然の移ろいを感じ、心のリズムも穏やかになります。焦らず、継続することを何より大切にしましょう。
参拝ノート・御朱印帳のすすめ
お参りした日や感じたことを記録しておくと、自分の内面の変化や成長がわかるようになります。「その日の天気」「参拝時の気持ち」「願ったこと」「学んだこと」などを簡単にメモしておくと、後から見返したときに心が温かくなるはずです。
御朱印帳も単なるスタンプ帳ではなく、“神様とのご縁を刻む大切な証”として扱いましょう。ページをめくるたびに、これまでの歩みや感謝の気持ちが思い出されます。御朱印をいただく際は、静かにお礼を述べるとさらに丁寧です。
ご利益を感じられないとき
「何も変わらない」と感じるときこそ、心の成長のチャンスです。ご利益は目に見える形ではなく、日々の出来事を通して静かに訪れるもの。焦らず、今ある日常に感謝し、周囲の人への思いやりを忘れないようにしましょう。
たとえば「今日も無事に過ごせた」「家族が笑っている」——そうした小さな幸せこそが、神様からの優しいメッセージです。結果を求めすぎず、感謝の気持ちを持ち続けることが、何よりも尊いご利益といえるでしょう。
よくある質問(Q&A)
Q:1日に何社まで参拝してもいいの?
→ 制限はありません。無理のない範囲で心をこめてお参りしましょう。とはいえ、数をこなすことが目的になると本来の意味から離れてしまいます。1社ごとにしっかりと感謝を伝え、ゆっくりと手を合わせる時間を大切にしましょう。1日で3〜5社ほどなら、無理なく心を保ったままお参りできます。遠出する場合は、途中の休憩や食事も神様からの恵みと捉えて感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。
Q:お願いごとを複数の神社でしてもいいの?
→ 問題ありません。同じ願いでも、感謝を添えることで誠意が伝わります。それぞれの神社にはご祭神の特徴やご利益があるため、神様に合わせた形で願いを伝えるとより丁寧です。
たとえば、学問の神様には「努力を続ける力をください」、縁結びの神様には「ご縁を大切にできますように」といったように言葉を変えるとよいでしょう。欲張るのではなく、神様への敬意をもってお願いをすれば、心の整理にもつながります。
Q:前にお願いした内容を変えてもいい?
→ もちろんOKです。人の気持ちは変わるもの。変化を素直に伝えましょう。過去にお願いしたことが叶っていなくても、それは「今のあなたに必要な経験をしている途中」と考えると気持ちが楽になります。
願いが変わったときは「以前のお願いを見守ってくださってありがとうございます。これからは新しい目標に向かいます」と感謝を添えて伝えるのがおすすめです。神様は常に私たちの心を見守り、変化を温かく受け入れてくださいます。
Q:他の宗教のお寺や神社を同日に回っても大丈夫?
→ 問題ありません。日本では神仏習合の文化があり、神社とお寺を同日に参拝することは昔から行われてきました。大切なのは順序よりも心。どこに行っても「感謝」と「敬意」を忘れずに、静かにお参りすれば神様も仏様もきっと穏やかに見守ってくださるでしょう。
Q:お礼参りはいつ行くのが良い?
→ 願いが叶ったときや節目を迎えたときに、改めて感謝の気持ちを伝えるのが「お礼参り」です。具体的な時期に決まりはありませんが、できるだけ早めに足を運ぶと気持ちが伝わりやすいです。手を合わせる際は「見守っていただきありがとうございました」と心を込めて祈りましょう。お礼参りをすることで、新たなご縁や学びがまた始まります。
まとめ|感謝の心をもって参拝すれば何社でも大丈夫
神社を巡ることは、神様を競わせる行為ではなく、ご縁を結ぶ尊い行いです。参拝を重ねるごとに、自分の心が少しずつ整い、穏やかに変化していくのを感じるでしょう。大切なのは「何社お参りしたか」ではなく、「どんな気持ちで手を合わせたか」。感謝と敬意を持って神様に向き合うことで、自然と日常の中にもやさしさや豊かさが広がります。
また、神社を訪れるたびに、その土地や人とのご縁も新たに生まれます。風に揺れる木々、参道を照らす陽の光、拝殿の静けさ——すべてが心を清めてくれる時間です。そんな一瞬一瞬を味わいながら、神様への感謝を積み重ねることで、自分自身もより前向きに生きられるようになります。どんな参拝も、感謝と誠実な心を忘れなければ、きっと神様は優しく見守り、温かく導いてくださるでしょう。